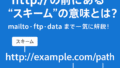はじめに
URLを見ると、なぜか「http://」のあとに“//”が付いています。
そしてその後ろには「www.」──昔から見慣れた形ですね。
でも実はこれ、どちらも「本当はなくても動く」 ものなのです。
今回は、URL構造の裏側と、Web黎明期の“名残り”を深掘りします。
“//”はいらなかった?──HTTP生みの親の証言
URL設計の父、ティム・バーナーズ=リー(Tim Berners-Lee) 氏は、
BBCのインタビューでこんな発言をしています。
「あの“//”はいらなかった。
当時のUNIX風構文に合わせただけで、
正直、タイプ数を増やしただけだったね(笑)」
— Tim Berners-Lee, BBC Interview, 2009
つまり、“//” は歴史的ノリでつけられた装飾。
URLは本来、こうでも問題なかったのです:
http:example.com/path
けれど世界中のブラウザがこの“//”を前提に動作してしまったため、
いまさら消すわけにもいかず、「伝統」になってしまったわけです。
“www”の時代──サブドメインが当たり前だったころ
1990年代、Webサーバーは「1台=1サービス」が基本でした。
そのため、用途ごとにサブドメインを分けて運用していました。
| 用途 | ドメイン例 | 役割 |
|---|---|---|
| Web | www.example.com | Webサーバー |
| メール | mail.example.com | メールサーバー |
| ファイル転送 | ftp.example.com | FTPサーバー |
当時のサーバーは単機能。
“www” は「Web用のマシン」の目印 だったのです。
現代では“www”なしが主流
しかし現在は、1台のサーバーで複数のサービスを動かすのが一般的。
Apache・Postfix・Dovecot・MariaDB・WordPress… すべて1台で完結できます。
そのため:
サブドメイン(www)はもう必須ではない。
たとえば、
https://hd0.biz/https://www.hd0.biz/
はどちらも同じサーバーに到達できます。
バーチャルホスト設定で www を省略しても問題なし。
今では「wwwなしURL」がむしろ主流です。
サブドメインの位置づけは“役割分け”から“整理用”へ
現代のサブドメインは、
実サーバー分割よりも「整理・分離・独立性」の意味で使われます。
| サブドメイン | 例 | 用途 |
|---|---|---|
blog. | blog.example.com | 別CMSやブログ専用 |
api. | api.example.com | システム用API |
cdn. | cdn.example.com | 静的ファイル配信 |
dev. | dev.example.com | 開発環境・テスト用 |
昔のように「1台=1ドメイン」ではなく、
1台で複数の仮想サーバー(vhost)を持つ のが今の常識です。
ドメインは「右から左に読む」
URLの中のドメイン名(hd0.bizなど)は、
左から読むのではなく、右から左へ階層的に解釈されます。
www.hd0.biz
└─ .biz (トップレベルドメイン) └─ hd0 (セカンドレベル) └─ www (サブドメイン)
つまり、最も上位は右端。
右側ほど「大きな区分」、左側ほど「個別の区分」を表します。
この構造が理解できると、
DNSやSSL証明書の仕組みもスッと入ってきます。
DNSとの関係:名前解決の進化へ
ドメインを右から左に解釈するルールは、
DNS(Domain Name System)の思想そのものです。
サーバーがどうやってhd0.biz → IPアドレス を解決しているのか、
より深い話は以下の記事で解説しています👇
次回予告
次回以降、第4回ではドメインの最後に付く「
/の正体」――
URLの“フォルダっぽいけどフォルダじゃない”謎を掘ります。
リンク
【ドメイン深掘り・第4回】:「/の正体!フォルダではないURLの裏側(HTML→PHP→WordPress)」
【ドメイン深掘り提案・第2回】「http://」の前にある“スキーム”の意味 mailto・ftp・dataから、http/httpsの本質まで